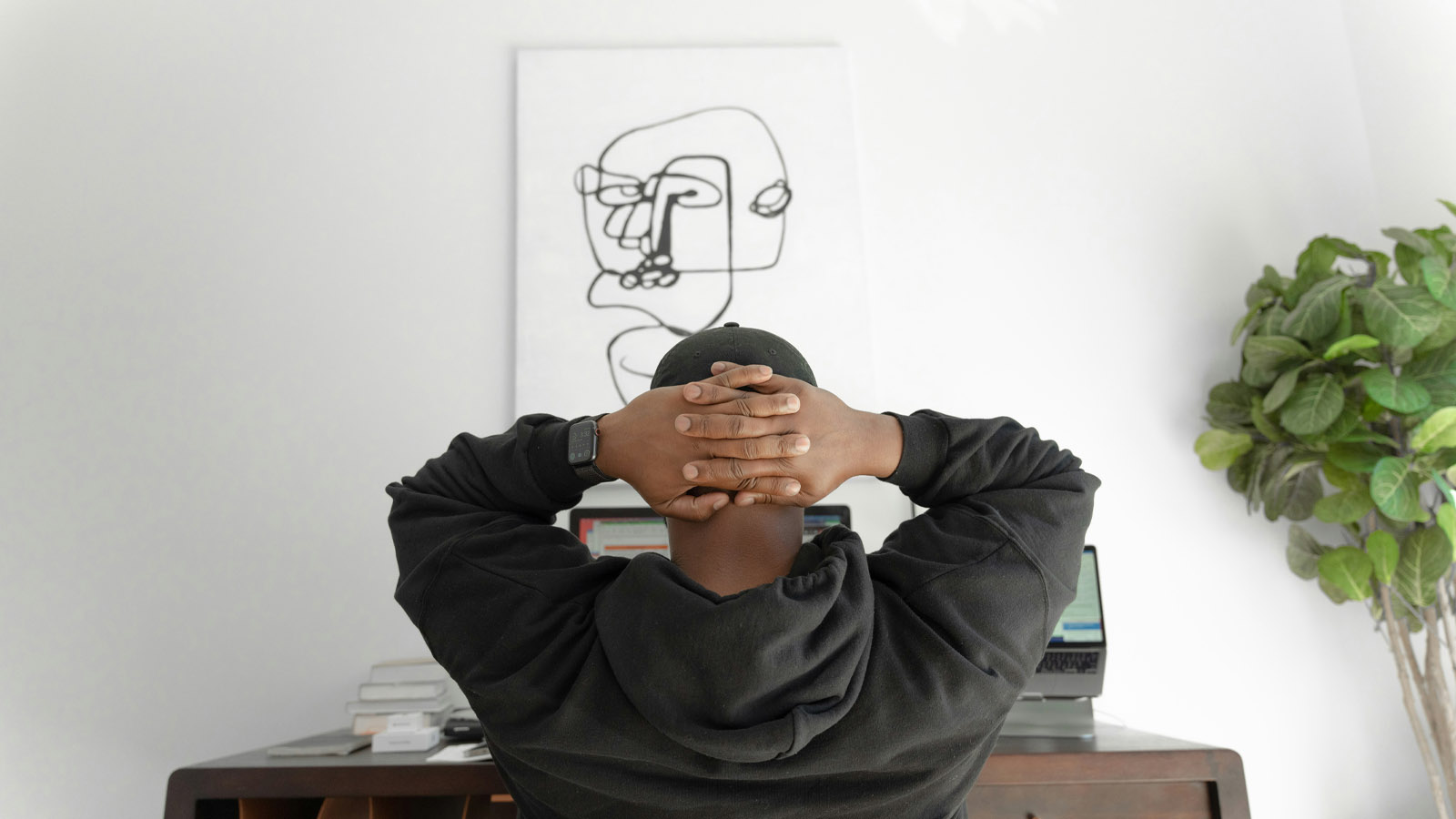
October 16, 2025
八十雅世 masayo_yaso
情報技術開発株式会社 経営企画部・マネージャー 早稲田大学第一文学部美術史学専修卒、早稲田大学大学院経営管理研究科(Waseda Business School)にてMBA取得。技術調査部門や新規事業チーム、マーケティング・プロモーション企画職などを経て、現職。2024年4月より「シュレディンガーの水曜日」編集長を兼務。
現代アートは、シンプルに生活を豊かにしてくれるものです。音楽、マンガ、小説、映画、スポーツなど、「それがなくて死ぬことはない」けれど「それがなくては生きた気がしない」ものは多く世にあり、現代アートもそれらの1つです。ただ、現代アートは、知らない人にとって少々とっかかりに困るものです。そこで、実生活に紐づけて、例えば現代アートとビジネスがどのように繋がっていくか、そして現代アートを道具として使えないか、を考えていきます。
その前提として、まず「ビジネス」というものがどのような要素から構成されうるのかを、把握したいと思います。要素分解にあたって、さまざまな切り口が考えられますが、今回はビジネスを真正面に学ぶ、国内の有名ビジネススクールの必修科目から紐解いてみることにします。ビジネススクールは経営に関する教育機関ですから、どの業界でも共通するビジネス要素を体系立てて捉えているだろう、という目算です。
例えば、早稲田大学大学院経営管理研究科では、「リーダーシップ」「マーケティング」「ファイナンス」「ビジネス会計」「人材・組織」「経営戦略」「ビジネス統計」「技術・オペレーションのマネジメント」の8つを、必修(2026年〜)として挙げています(早稲田大学 大学院経営管理研究科 新時代のビジネススクールを目指して)。慶應義塾大学大学院経営管理研究科の必修科目は、「会計管理」「マーケティング」「経営科学」「組織マネジメント」「経済・社会・企業」「財務管理」「生産政策」「総合経営」の8つです(慶應義塾大学大学院経営管理研究科 カリキュラム・各科目の概要)。さらに、一橋大学大学院経営管理プログラムでは、「経営戦略」「マーケティング」「財務会計」「企業財務」「経営組織」「マネジメント・コントロール」「企業データ分析」「経営哲学」の8つが必修科目です(一橋大学大学院経営管理プログラム 科目詳細)。
こう並べて眺めてみると、各校完全一致にはなりませんが、「経営戦略」「組織マネジメント」「マーケティング」「会計・ファイナンス」「データ分析」あたりが、共通項として浮かび上がってくるように見えます。
そして、この中では特に「経営戦略」「組織マネジメント」、そして「データ分析」の一部に対して、現代アートは効くと、私は考えます。現代アートは常に新しいコンセプト求め、問いを投げかけるため、その姿勢が、これらのビジネス要素に効果をもたらしてくるのです。
「マーケティング」についてはいささか毛色が異なり、現代アーティスト自体の戦略性が参考になるかもしれません。一方、「会計・ファイナンス」といった、ルールや方法論が確立されているものについては、現状、そこまで深く影響を与えないでしょう。
ということで、「経営戦略」と「組織マネジメント」を中心に、若干「データ分析」「マーケティング」を挟みつつ、現代アートのビジネスシーンにおける効果を考えていきます。
組織マネジメントは、どの会社であっても肝要であり、悩みの種です。特に近年は社会のグローバル化に伴い、組織を構成する人員が、性別、国籍といった属性的な点はもちろん、価値観においても多様化しています。
大島洋氏は、この多様化する時代における組織マネジメントに対し、“人材の多様化を踏まえ、個々の状況と人材の特性に応じて、異なる育成手法を取り入れ、使い分けることが重要である。そのためには、これまでの一面的な思考パターンから脱し、多様な現実を構造的に理解するための多面思考力を養っていくことが、必要不可欠の条件である”と説きます(『ビジネススクールで学ぶ人材育成 「多面思考」で個性を活かす』)。
私たちは個々のバックグラウンドや経験をもとに、何かしらのフィルター、認知バイアスをもって物事を見てしまいます。これを完全に無くすことは難しいかもしれませんが、見方・視点を増やすことで、認知バイアスを減らす努力は可能でしょう。
この多視点をもつことに、現代アートは有効であるといえます。私たちが会社における多様性に悩むのと同時に、私たちと地続きで生きる現代アーティストたちも多様性に対峙し、「問い」を投げかけながら、作品を生み出しているのです。
2021〜2022年に、東京・六本木の森美術館で展覧会「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」が開催されました。そこで取り上げられた1人、スザンヌ・レイシー氏は、“コミュニティとの対話を通じて、女性解放運動や人種差別、高齢化、暴力などの社会的課題や都市の問題に取り組んできた”アーティストです(森美術館「アナザーエナジー展:挑戦しつづける力―世界の女性アーティスト16人」公式サイト)。本展覧会ではレイシー氏による《玄関と通りのあいだ》という作品が展示されました。この作品は、“2013年10月19日、365人の活動家がブルックリンの住宅街の一角に集まって行われた壮大なスケールのパフォーマンス”であり、“黄色いストールを身に着けた参加者が60のグループに分かれ、玄関と通りのあいだの階段に座り、人種、民族的アイデンティティ、階級、フェミニズムなど様々な問題について話し合い”をした様子を映像で流しています。当時、私が鑑賞した際、映像の他に「Whose LABOR is invisible?(誰の労働が見過ごされている?)」というメッセージが書かれたベンチがあり、それにドキッとした記憶があります。「私は誰かが見えないところで支えてくれていることに、無頓着かもしれない」と気づかされたのでした。
なお、本作品は、現代アートのジャンルとしては、ソーシャリー・エンゲージド・アートに属するとされます。ソーシャリー・エンゲージド・アートとは、アーティストが社会に積極的に関わり、対話や協働のプロセスを通じて社会的な課題に取り組み、何らかの変革をもたらすことを目指すアート活動のことを指します。
昨今はVUCA――Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の時代と呼ばれ、先の読めない環境下であるといわれています。ちなみに、VUCAという言葉自体は、米ソ冷戦後にアメリカで使われた軍事用語がもととなっているそうです。そうなると、物心ついた頃からVUCAを生きる私には、むしろVUCAじゃない時代がよくわかりません。とはいえ、日々様々な変化に追われ、世界が繋がっているがゆえに「風が吹けば桶屋が儲かる」とばかりに、不意の影響を被ることへの実感はあります。
閑話休題。さて、そのような先が読めない状況であっても、会社の経営において、未来を考えることは避けられません。近々数年後の未来だけでなく、10年後といった長期スパンの未来も視野に入れる必要があります。杉田浩章氏は、多くの経営者の悩みは、短中期的な構造改革と収益改善にとどまらず、自社の存在価値を問い直し、自社であるがゆえの価値を世の中に提供し、長期的に成長できる企業としての基盤を再構築することであると指摘しています。そしてその背景として、“かつての成長を支えられてきたコア事業のベースとなる事業ドメインの捉え方の賞味期限が切れつつある、あるいは今までの自らの市場であると定義したドメインの中で、いかに最適な競争戦略を繰り広げても、そこに将来はない、という認識が生まれていること”を、挙げています(『10年変革シナリオ 時間軸のトランスフォーメーション戦略』)。
長期的な未来をみすえたい。けれど、変化が激しくてどうなるか予測できない。過去の経験も役に立たない。そのような時に利用する手法として、シナリオ・プランニングというものがあります。過去の情報をもとに1つの「正解」となる未来を予測するのではなく、さまざまな可能性から複数の未来(シナリオ)を描き、それぞれに対応する戦略などを考える手法です。
実はこの「未来のシナリオを考える」ことは、現代アート/デザインの得意領域の1つです。秋元雄史氏は、著書『アート思考――ビジネスと芸術で人々の幸福を高める方法』にて、アーティストを「炭鉱のカナリア」に喩えています。秋元氏は“彼らはまだ多くの人が見えていないものをいち早くその目で見て、聞こえていないことを聞きながら、言語としては表現しようのないものを形やイメージに置き換えて伝えている”といいます。アーティストたちは、私たちがまだ感知しない未来に対してもアンテナを立てているのです。
例えば、アート/デザインの領域では、スペキュラティブ・デザイン(Speculative Design)という、シナリオ・プランニングに近いアプローチを取るジャンルがあります。アーティストの長谷川愛氏は、このスペキュラティブ・デザインを用いた作品を発表しています。例えば、《シェアード・ベイビー/Shared Baby》というプロジェクトでは、“遺伝的に複数の親を持つ子どもが実現したら、子育てはどう変化するのか”という疑問にもとづき、バイオテクノロジー、倫理、子育て、あらゆる視点で思考実験を行い、現在の私たちが抱える問題を浮かび上がらせます。(112 長谷川愛(アーティスト / デザイナー)前編|六本木未来会議 -デザインとアートと人をつなぐ街に-)
会社で「シナリオ・プランニングをしよう!」と意気込んでも、日々の思考のクセから抜け出せず、複数のシナリオを生み出し切れないことは、ままあることです。目の前にある問題解決に勤しむことと、未来の理想像を描きながら「問い」を立てることを、1人の人間の脳内で両立させるのは、なかなか困難です。そのような時は、自分だけや、自分と似た思考回路をもつ人とだけ考えるのをやめて、日常で会うことのないアーティストが未来をどう捉えているかに触れられれば、少し頭がほぐれるかもしれません。
次回はこの続きとして、データ分析、マーケティング、イノベーションといったキーワードと、現代アートについてお話しできればと思います。