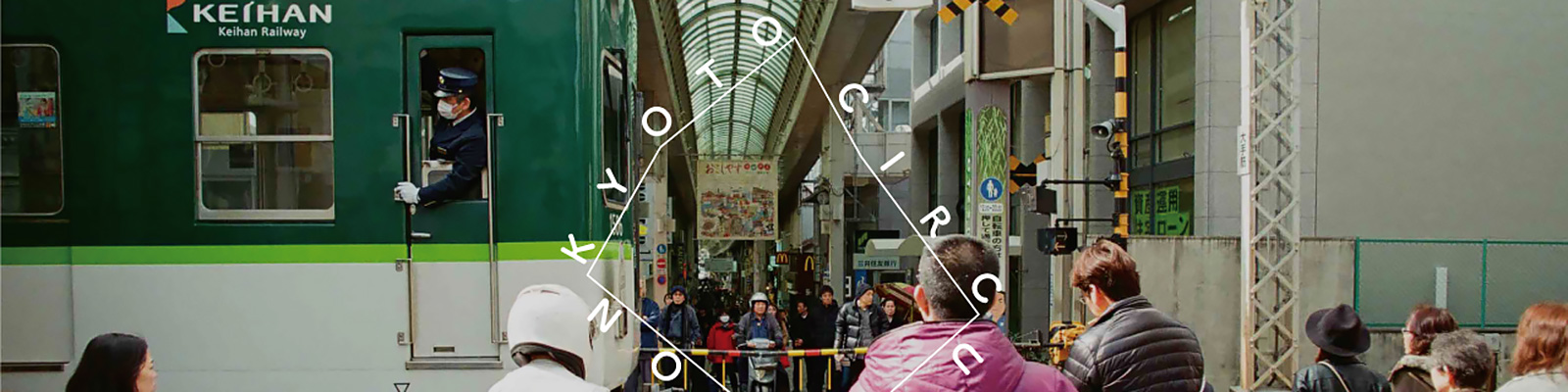
November 28, 2017
影山裕樹 yuki_kageyama
1982年生まれ。編集者、プランニング・エディター。雑誌編集部、出版社勤務を経て独立。アート/カルチャー書のプロデュース・編集、ウェブサイトや広報誌の編集のほか、各地の芸術祭やアートプロジェクトに編集者/ディレクターとして関わる。著書に『大人が作る秘密基地』(DU BOOKS)、『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)。「NPO法人 芸術公社」メンバー。OFFICE YUKI KAGEYAMA:http://www.yukikageyama.com
ロームシアター京都という劇場がハブとなって、京都市の財団が運営する複数の文化会館と連携し、一般市民参加のもとローカルメディアを作るワークショップのプログラム、「CIRCULATION KYOTO〜サーキュレーション キョウト〜」が目下、進行中である。僕はこのプロジェクトのディレクターとして参加し、デザイナー、編集者、リサーチャーなど異なるスキルを持つクリエイターとともに、全5回のレクチャーを通して市民参加型メディアを構想、2018年3月には実際の発行まで持っていくことを目指している。
▼「CIRCULATION KYOTO」ロゴ(写真:成田舞)

このプロジェクトが異色な点は二つある。一つは、劇場という、本来芸術作品を制作・興行する拠点が主体となり、作品制作ではなく、メディアを作ることを目的としたプログラムを組んでいること。もう一つは、今回ロームシアター京都が連携する五つの文化会館が、いわゆる京都の中心部(洛中と呼ばれる)ではなく、その少し外側(とはいえ京都市内ではあるのだが)に位置していること。
タイトルにもあるとおり、これら京都市内の“外縁部”をCIRCULATION(循環)しながら、各地域に共通する課題や、いままでにない京都のイメージを掘り起こそうという意図がこのプロジェクトには込められている。僕たちプロジェクトメンバーは、昨年の冬から今年の春にかけて、これらの文化会館が位置する5地域(山科区、伏見区、西京区、北区、右京区)に何度も通いながら、周辺の住民や、まちづくりNPOや企業、金融機関などの担当者に会って、これら地域の特色、課題をヒアリングしてきた。その中で見えてきた知見を参加者と共有し、また、彼ら地域のキーパーソンとのネットワークを活かしながら、いままでにない、「京都」のローカルメディアを構想したいと考えている。
井上章一氏は『京都ぎらい』の中で、洛外出身者が洛中の人々に対して抱いている複雑な感情を吐露している。「東京のメディアが洛中の人間をおだてるから彼らはつけあがるのだ」という趣旨のことも書いている。東京から京都にやってきた人間は正直、その微妙な感覚は共有できない。というか、関東出身者がいちばん憧れを抱く地域といえば京都だし、いざ訪れればディスカバー・ジャパンのキャンペーンや各種広告、雑誌の特集に洗脳され、完全に浮かれた観光客として振る舞ってしまいがちだ。
▼郊外の団地群(写真:成田舞)

しかし、僕たち観光客がイメージする京都は、本当に狭い範囲であることに気づかされる。電車に10分も乗れば、西は桂川を越えるし、東は山科まで行けてしまう。しかし、これらの地域は郊外のキャンパスに通う学生でなければ頻繁に訪れる機会もないだろう。
実際、風景が違う。特に興味深いのは、高度成長期に造成された洛西ニュータウンや醍醐石田団地などの巨大な団地群だ。当然ここでは首都圏と同じように、高齢化や空き家、治安や老朽化の問題を抱えている。今回のプロジェクトが目指すのは、観光客(あるいは京都の中心部の生活者さえも)が知らない、もう少し広いレンジで見た京都のイメージを「ローカルメディア」によって浮き彫りにすることである。
そもそも対象エリアは、酒どころと伏見稲荷大社で知られる伏見区、山を一つ隔てた山科区など、地域ごとの文化・環境の違いが甚だしい。果たして、これらの地域全体としての共通点は見い出せるのだろうか。さまざまな人にヒアリングする中で、特に印象的だったのが、奈良文化財研究所の惠谷浩子さんの話だった。
京都は五山の送り火で知られるように、周囲を山に囲まれた盆地に綺麗に収まっている。そして、西に愛宕山、東に比叡山と、篤い信仰を集める二つの山に守られている格好だ。どこまでも続く関東平野の茫漠とした風景とは明らかに異なる。そして、惠谷さん曰く、「これらの山々で採られた一次生産物を、その近くに位置する周縁部の地域の人々が『加工』し、都の中心部へと届ける役割を担っていた」というのである。
「具体的には、山間部のクマザサを利用して祇園祭の厄除ちまきをつくる地域があったりします。また、各々の加工生産物のルートを逆に辿り、都の文化が外に広まっていったという側面もあります」(惠谷さん)。他にも、海が遠い京都だからこそ生み出され、洗練されてきた鱧や鯖寿司、すぐきや菜の花の漬物などの食文化……そうしたモノの物流の経路と文化の伝播がうっすら垣間見えるという。
ある意味、京都の外と内の“エッジ”にある地域が、都の文化を成り立たせる「フィルター=メディア」となっていたわけだ。こうした視点で京都のまちを見ることができるとしたら、例えば加工した木材の端材で作った建材や、あまった食材で作る、その地元にしか存在しない「まかない」のような料理から、境界を担う地域の共通点が見えてくるかもしれない。
▼惠谷浩子さんを囲んで、プロジェクト・メンバーで議論した。

京都駅を起点に中心部をぐるっと回る市バス206系統のルート周辺を巡ったエッセイ『京都の平熱』の中で鷲田清一氏は、「街をやんわり包む鄙(ひなび)」と、坪庭など「町家の中に組み込まれた鄙」との間に、都は二重に挟まれていると語った。郊外の田舎性と市中の都会性が往還し混じり合って成り立つ都市の性格の一端を言い当てているように思う。そう考えると、こうしたモノと文化をまちの外と内へと行き来させる“運び屋(キャリアー)”として、これらの地域の人々が担ってきた役割は大きいのかもしれない。
今回のプロジェクトメンバーでもあるリサーチャーの榊原充大氏は、ネット上で話題になった「京都人の脳内地図」を引き合いに出しながら、この地図の中で「一応京都」と思われている地域を、洛中との関係ではなく、「“周縁”にあるという共通点」によってつなげてみたい、と語る。
先ほどの構図に従えば、外と内をつなげる物流の経路はそれぞれ縦に延びていた。おそらく、「京都の七口」へ通じる街道沿いに物流の経路があったのだろう。そのため、これらの地域を環状に移動する人や物の経路は見えてこない。しかし、市バス206系統のさらに外側、郊外型のショッピングセンターにだけ荷物を配送するドライバーが巡る道路を線でつないでみるとどうだろうか。そこから、京の文化を下支えしてきた“周縁”地域の共通点をさらってみる。面白いことに、京都にあるニトリの店舗はこれら“周縁部”に点在している。ニトリに通う生活者のメンタリティをリサーチしていってもいい。ローカルメディアを作る手がかりは、こうした「見立て」から始まるように思う。
その後、ローカルメディアワークショップCIRCULATION KYOTOは公開プレゼンテーションを終えて、現在は本格的に各チームがメディアを制作する段階に入っている(プレゼン映像が公開されているので、こちらのHPを参照のこと)。約1ヶ月半かけて、異なるバックグラウンドを持つ参加者たちが、自らの役割とスキルを持ち寄って、非常に完成度の高いプレゼンを行った。観覧に来てくださった地域の企業や団体の方々からも概ね好評で、各プランに具体的に支援を買って出てくださるところも現れ始めた。
▼カードを使ったワークショップの様子。

ワークショップはよく、アイデアを発表して終わりになることが多いけれど、こうして実現性の高いプランを目にすると、それが不可逆なうねりとなって、市民を巻き込んで活動として残っていく。それは、今すぐに地域の課題を解決するには役に立たないかもしれないけれど、5年後、10年後には確実にその地域に足跡を残すことになると思う。
※この記事は「マガジン航」での連載「ローカル・メディアというフロンティアへ」から再編集のうえ転載したものです。