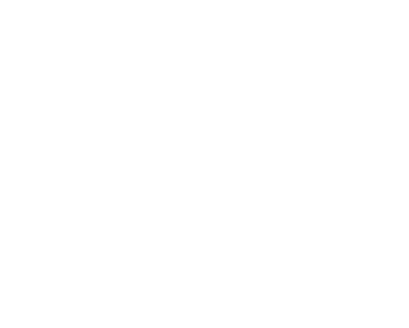地方創生にはさまざまなアプローチがあるが、その手段の一つとして企業の持つ最新技術を地域で活用することが挙げられる。専門的技術や最新の商品を用いて地域での課題解決の糸口とするこの手法は、大手企業に限らずベンチャー企業と地方のマッチングも含めて内閣府でも推進している。とはいえ、決して一筋縄でいくものではない。
2021年5月20日、金沢工業大学(KIT)において「金沢工業大学 INNOVATION HUB 2021地方創生フォーラム~“ひと”中心で生み出す地方発イノベーション~」というオンラインイベントが開催された。まさにこの、地方創生における企業の技術導入の是非や問題点にフォーカスしたトークイベントだ。
同イベントのトークセッションでは、地元企業である北菱電興と農事組合法人んなーがら上野営農組合が共同運営する、イチゴのハウス栽培拠点「いちごファームHakusan」が紹介された。本稿では、当事者らが語るこの「成功事例」に注目しつつ、地方創生 × 技術導入の難しさや留意点について見ていきたい。
「便益」と「不便益」。住民の心に沿った地方創生の技術導入とは?
トークセッションの議長は、金沢工業大学(KIT)情報フロンティア学部心理科学科神宮英夫教授。まず神宮氏による基調講演の内容を大まかに振り返りたい。
神宮氏の研究範囲は、人々の潜在意識を可視化することだ。神宮氏はこれを「なんとなくの見える化」と呼んでいる。詳しくは、過去の「創生する未来」の記事を参照していただくとして、ここでも簡単に触れておこう。
例えば自動車の乗り心地を評価するとき、乗車した人は実際には視覚や聴覚、振動(触覚)など多感覚の情報を同時に得ている。しかし、これらを評価する段階になると適切な言葉にならなかったり、選択式の評価基準を設定しようにもそもそも問い自体がうまく立てられなかったりする。企業がマーケティング調査などを行う際に、顕在化させることが難しく埋もれてしまう感覚があるわけだ。
結果、消費者が得る感覚とは乖離してしまい、売り上げの拡大にはつながらないということがある。そのズレを埋めるために、こうした潜在的に「なんとなく」得ている感覚をデータ化し分析することが神宮氏が研究しているテーマである。

この「なんとなくの見える化」が地方創生の場面においても援用できるのではないか、というのが講演の内容だ。神宮氏は岩手県大槌町の震災復興の事例を挙げてこう説明する。
「岩手の被災地は帰還率が悪いわけです。堤防を作って嵩上げの工事をしましたが、なかなかうまくいかない。例えば大槌町は、昔から美味しい水がたくさん湧き出ていた土地なんですね。現在、三陸ジオパークという形で整備されているのですが、調べたらこういう写真(下掲写真参照)にぶつかりました。これは嵩上げ工事の時に、湧水地を埋めるためにお祓いをしている写真です。つまり、地域の人にとっては、それだけ湧水地が重要なファクターだということです。湧き水とともに生活をしていて、それは日常的で当たり前の風景でとても重要なことだったということです。でも、それを潰して嵩上げせざるを得なかった。この土地が大切な湧水地であることは日常の当たり前のことなので、復興作業が進んでいく中でも地域の人はなかなかそれを口に出して言えなかった。あるいは明確に意識していなかったのかもしれない。復興に際して、その思いが『見える化』できていなかったんじゃないかなと感じました」
地域住民にとって、湧き水は地域そのものを体現する非常に重要な要因だった。しかし、それらは埋め立てられてしまった。元あった帰るべき自分たちの土地は消失し、帰るべき土地ではなくなってしまった。こうして地域住民の心情を「見える化」できないまま復興作業が進んでしまったために帰還率が低いままになっているのではないか、と神宮氏は推察する。
神宮氏が指摘するもう一つの点は、技術導入における「便益」の在り処だ。
科学技術の進歩は我々に何某かの「益」をもたらす。このことは疑いないように思える。しかし本当にそうだろうか。
技術を保有する側の企業は、地方創生の局面でもその技術を導入することで地域社会が発展したり、維持できたり、新たな価値を生み出したりできるものだと信じているだろう。この点に神宮氏は「待った」をかける。
神宮氏は、自動車の自動運転技術を例に「便益」の別の側面を指摘する。「自動運転は労力をかけずに車を運転できるために便益をもたらすものと考えられています。しかし一方で、運転する楽しさは奪われてしまうし、なんとなく感じていた自己効力感やエフィカシー(有能感)を感じられなくなってしまう。むしろ不便であることの方が『益』なのではないか、というのが『不便益』の考え方です」

つまり一見、不便に思われる地方の日常的な暮らしの中に、実は地域住民が潜在的に感じている「益」があるのではないか、「科学技術」の名の下にそれらを無自覚に排除してしまうことに問題はないのか、という問いかけだ。地方創生を目指して技術導入する際にも、地域住民のなんとなく抱える潜在的感覚を「見える化」する必要があるのでは、というのが神宮氏の考えだ。
「地域が持っている文化やしきたりなども技術展開するときに考えるべき重要なポイントになると思います。そういうところを多少なりとも見える化できると、技術導入が地域の中に十分に受け入れてもらえる。地域の人たちがハッピーになる技術導入になっていくんじゃないかな、と思います。これらを少しでも見える化することで、今までとは違う、住民の心に沿った地方創生の技術導入につながるのではと思います」(神宮氏)
そして、神宮氏がこの成功例だと評価するのが、「いちごファームHakusan」だ。どんな施設なのか。
未来の地域社会を支えるマイクロ水力発電を用いたイチゴハウス栽培
「いちごファームHakusan」は、イチゴの摘み取り体験ができるビニールハウス施設で、石川県内の過疎地域の一つである白山市内に建つ。ハウス内では、「章姫」「紅ほっぺ」「かおり野」など5種のイチゴが栽培されている。老若男女が屈まずにイチゴを摘み取れるよう地面より高い位置に棚を組み高設栽培されているのも特徴だ。これは、果実が地面に触れないため衛生的な栽培方法ともされている。

▲5種のいちごを高設栽培する「いちごファームHakusan」
この施設に供給される電力には、地元企業である北菱電興が開発したマイクロ水力発電システムが用いられている。引水地点から11メートルの落差で生じるエネルギーを用いて電力を生み出し、それを圃場に供給する。電力が余った時は温水を生成し、逆に電力が足りなくなった時は商用電力を受電する「給電ハイブリッドシステム」を採用している。
マイクロ水力発電(小水力発電)とは、上下水道水や農工業用水の排水といった未利用の水エネルギーを活用して電気をつくる小規模な水力発電のこと。概ね1000kW以下の発電をこう呼ぶ。日本では、2004年頃から少しずつ導入されてきており、自然エネルギー利用の観点から技術進歩してきた。小規模の熱電供給で充足するような地域社会を支えるエネルギー源として、地方創生の観点から注目されている。

▲地域社会を支えるエネルギー源として注目されるマイクロ水力発電
トークセッションに登壇した北菱電興の酒元一幸氏は、この取り組みを「エネルギー × 農業 × ICTの可能性」を示すものだという。「冬季に時間をかけて成長させる地元の気候を生かした高品質なイチゴの生産と、地産地消の効果の最大化を目指しています。また、未来のイチゴ摘み取り体験の機会を提供し、農業従事者の負担軽減をICTで提言しています」
この「いちごファームHakusan」が地方創生の成功例だと考えられている理由は、この施設ができたことで地域内外からの人流が生まれ、企業間の繋がりも生まれ、「地域が活気づいてきた」と地元住民の声からも確認できるからだ。しかし、いきなり成功したわけではない。成功までの道のりの中には、注目すべき「地方創生 × 技術導入」のポイントが隠れている。
プロジェクト発足までの道のり
当然のことではあるが、企業とは利益を求める組織だ。地域に貢献することが求められたとしても、まずは企業に利がなければならない。企業からすれば、結果として地方創生に資することができれば御の字であって、それ自体を目的とはし難いものだ。では、北菱電興はどのようにこの取り組みに踏み切ることができたのだろうか。

酒元氏によれば「社内の理解を得られたのは外部からの影響があったから」だという。
「プロジェクトを立ち上げるときには、収益の見積もりを作ってそれを元に進めていきましたが、プロジェクトに関わっていない他事業部の社員にはなかなか理解が得られませんでした。どんな企業でも、組織が大きくなると同じ悩みはあると思います。しかし、KITなどの協力もあり取り組みを外部に発信できて、SNSなどでも広まり社会の目が変わってきたことが、社内の考え方が変わるきっかけになりました」(酒元氏)
酒元氏は「自社の技術を地方創生に役立てたい」という強い思いを持っていたが、自社に対する社会の目が変わったことが社内の理解につながり、プロジェクトを勧められるようになったという。

一方、地域住民側にも企業のプランを受け入れる体制が必要になる。いくら地域のためになる技術や商品であっても、住民側がその「益」を理解しなければ地域への技術導入は絵空事で終わってしまう。「地方創生」という美しい言葉を大上段に掲げたプロジェクトであっても、地域側も通常の仕事に加えて人的リソースを割くわけで、その「益」を共有できなければ進まない。
同じくトークセッションに登壇した農事組合法人んなーがら上野営農組合理事長の中西盛重氏の話からは、プロジェクトを受け入れにはいくつかの偶然が重なったことが窺えた。
「この話の2年ほど前、近畿大学の学生さんが夏合宿でペットボトルを使って用水路で発電しているところにたまたま参加させていただいたんです。『こんな小さな用水路でも発電できるのか』と、その時、少し関心を持ちました。2年経って、これもたまたまですが部下に北菱電興の元社員がいまして。『北菱電興からこういう話があるんですが、どうします?』と聞かれました。それで、一応話を聞いてみようと思いました」
「地方創生に技術導入を」というスローガンはそこここでよく見聞きする。しかし、地域住民との価値共有が難しくて失敗したり、理解が進まないままに企業や行政側が推し進めてしまって後にトラブルになるような例もある。偶然もあって、同プロジェクトではこのハードルを比較的スムーズに越えられたのだ。
「話を聞いてみると、マイクロ水力発電という思いもよらない話でした。興味深い話を繰り返し聞くうちに、熱意が伝わってきて信頼関係が生まれたと感じています」(中西氏)。
神宮氏は「企業と地域がどれだけしっかり繋がれるかが、成功の第一歩。おそらく、マイクロ水力発電を導入しよう、という話を企業が持ちかけるだけでは地域に受け入れられなかったんじゃないかと思う。それを農業というカタチ、そのなかでもイチゴ栽培というカタチが地域の人たちのニーズに沿った展開だったのではないかなと考えます」と評した。
水利権の障壁を越えられた幸運
プロジェクトを進める上では、一つの大きな幸運にも恵まれた。マイクロ水力発電は、文字通り水の流れ=水力を用いて発電する。民間がこの自然エネルギーを利用するにあたって壁となるのが、「水利権」だ。河川などの流水は誰でも勝手に利用できるわけではない。流水の利用は河川法によって規定されているからだ。

▲マイクロ水力発電の設置には幸運にも恵まれた
んなーがらの中西氏はこう話す。
「正直、水利権の関係は非常に厳しいところがあります。私どもも県庁等々を訪問して、水利権の元となる考え方そのものから勉強しました。今回、マイクロ水力発電をしている場所が、慣行水利(権)で、農業用に使うものですが農業用水からは外れており、最後の排水処理する河川だったことが幸運でした。そこで県に何度か足を運びまして確認を取り、その中で(使用)許可を得ることができました」
慣行水利権とは、江戸時代に成立した水利慣行に依拠するもので、長期にわたり継続かつ反復して水を利用してきたという事実があり、その排他的支配が該当地域の社会通念によって承認されているものを指す。つまり、「いちごファームHakusan」が利用したい流水が、近隣の地権者や行政などと相反することなく利用できるものだったため、スムーズに事が運んだのである。
中西氏は続ける。「土地改良などが絡むと、許諾料などが発生はするんでしょうけれども、慣行水利ということで、外部との折衝等なしに私どものなかで判断できた。その点は一番ラッキーだったと思います」
地方創生 × 技術導入というプロジェクトにあって、第一のハードルとなるのは地域住民と企業側の理解の共有だということは前述した通りだが、これを乗り越えたとしても、実際に事を運ぶにあたっては、権利や利権、法制度上の問題に当たることが多々ある。時間をかけた交渉が必要になったり、プロジェクトの方針を変える必要があったり、余計な出費が発生する場合もあるだろう。しかし、このプロジェクトにおいては、ラッキーなことにこれらの障壁が比較的少なく済んだのである。
地域住民に受け入れられていく手応え
「いちごファームHakusan」の取り組みには、マイクロ水力発電という「クリーンエネルギーの利用」や「エネルギーミックスの実証」、「無農薬農業の可能性の提示」、「農作業の短縮や軽減かの実証」といった他の地域でも援用可能な技術の実証実験の場としての機能もある。「輸出できる地方創生プロジェクト」という側面からも、注目すべき取り組みだ。
だが「現場」では、これらの意義を超えてさまざまな広がりが生まれているという。

「最初は、イチゴ摘み取り体験という形でお客さんだけに来ていただいていたのですが、2年目のシーズンから(地元の)鳥越小学校の3年生の社会科の課外授業でも使ってもらっています。7月の中旬にイチゴの子株を取り、9月中旬に自分で取った株を定植(植えて)、2月、3月で自分で植えたイチゴを収穫するという体験学習を行いました。子供たちはみんな目を輝かせて植えたり収穫したりしてくれました。後日、先生や生徒からお礼の手紙をいただいたんですが、その時に担任の先生から『生徒みんなで、これからは町の特産品にイチゴって書けるねっていう話をしていた』と聞いた時に、やってよかったなと思いました」(中西氏)


また、近隣の農家が育てた野菜を「いちごファームHakusan」で販売したり、地元のフルーツ専門店やジェラート店と連携した商品の開発・販売をしたりと、地域住民らと協働する場としての機能も生まれてきた。
こうして地域住民側に受け入れられていく手応えを中西氏はこう語る。
「人がどんどん押し寄せてくるようになりました。地元の人たちには最初から『すごいなぁ』と言ってくれる人もいましたが、半面、冬の雪の関係で『あのハウスは絶対つぶれるわ』というようなことも言う人もいました。それにもめげず、たくさんの人たちが『いちごファーム白山はあの場所だ』ということを認識して地域を代表するような名前になってきたということが、地元としてはかなり嬉しい部分です」
企業側の意見として酒元氏はこう話す。
「地元の方々に愛されて、そこに集まる関係人口も増えてきた。企業としても『いちごファームHakusan』がシンボル的なものになってきた。でも、弊社のものというよりは、地域のものだと感じています。ただ、当初はこうなることは想像できませんでした。関わる方々と何をするかと、どういうことを目指すのか、ということまで一緒に話ができる関係を築いていくことが大事だと思います。地方創生での技術導入という側面では、(企業、住民が)お互いに納得感を得て、理解を共有し、長く持続していくために地元の方々や関係する方々と一緒に方向性を考えながらやっていくことが必要だと思っています」(酒元氏)

神宮氏も心理学的観点からこう総括した。
「地域と一緒にイチゴファームが成長していると思うのですが、そのことも『やるぞ』と思ってやっているというより『上手に回っていった』と感じます。いろいろなラッキーが重なったのかもしれませんが、地域の人たちと一緒になってやっていこうという意識が、地域の人たちに受け入れられる大きな要素になったんじゃないかと考えています。地域住民に寄り添う意識というかニーズに沿う形の展開が、結果として上手に回っていった、と思います」
さまざまな「益」をもたらす場として地域住民にも認知されるようになったからこそ、今では「成功例」と呼べる。しかし、その過程が平坦であるはずがない。地方創生 × 技術導入の場面では、企業側が地域住民に寄り添う「意識」、そして地域住民側がそれを理解しより良いものにしていこうという「意識」が何より必要だ。そうした「互いの意識」のすり合わせを間断なく続けることで、双方の「益」を共有でき、誰もが求める地方創生につながる。実は、これこそが最も難しいことなのかもしれない。
なお、KIT地方創生研究所では企業のメンバーシップを募集している。(詳細はこちらまで)
(取材・執筆:杉田 研人 写真:土屋香奈 企画・制作:SAGOJO)

![]()
![]() Sponsored by 金沢工業大学
Sponsored by 金沢工業大学