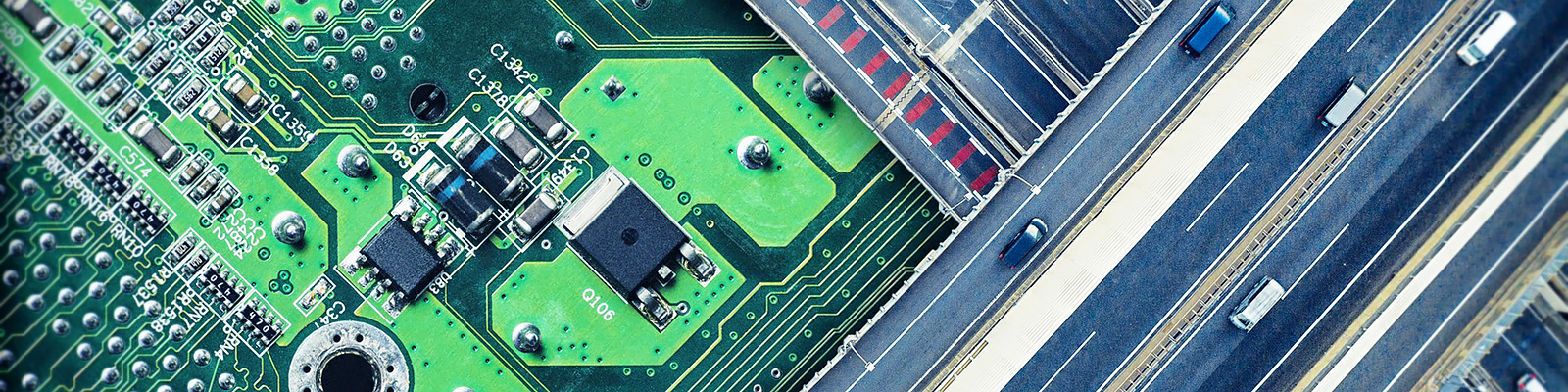
画像はイメージです original image: © metamorworks - Fotolia.com
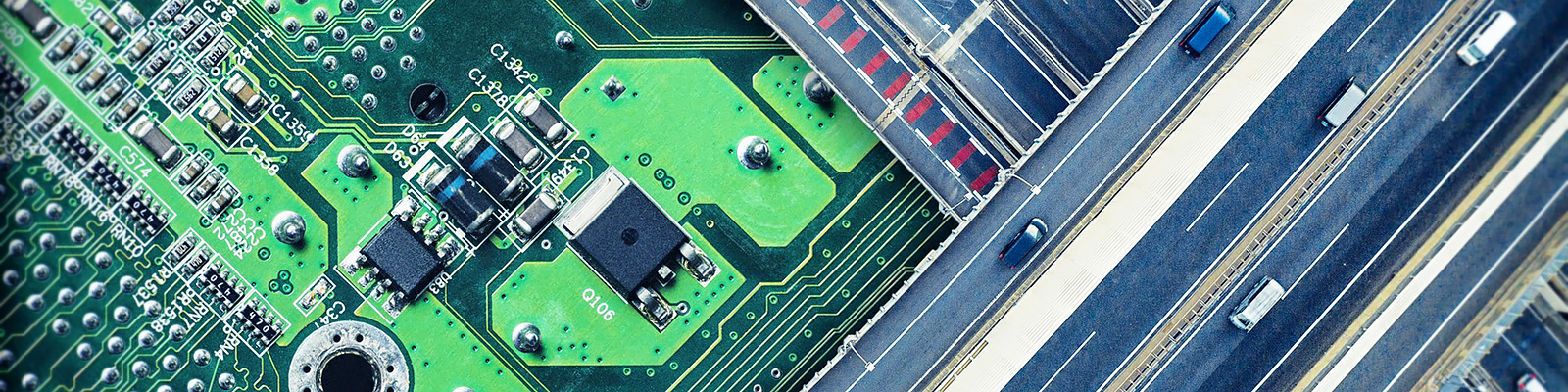
画像はイメージです original image: © metamorworks - Fotolia.com
かつての新しい交通手段の登場と普及はわれわれの生活を大きく変えてきた。19世紀にヨーロッパの都市構造を変容させた交通機関が鉄道だったとすれば、20世紀のアメリカでは自動車がそれに代わったといえる。近代を迎え、建築のレベルでは、鉄、コンクリート、ガラスが主要な材料となり、世界中に同じようなビルが並ぶ風景を出現させた。例えば、壁構造から柱梁の構造にシフトし、壁が荷重を負担する必要がなくなることで、ガラスのカーテンウォールに包まれた高層ビルも日常化している。こうした前提に対し、自動車は、どこにどのような用途の建物をいかなる密度で配置するか、といった状況に影響を与えた。アメリカでは フォード社が安価な大量生産に成功し、1920年代までに800万台の車が全土を走るようになった。かくして公共交通機関に縛られない、個人の自由な行動範囲が広がると、都市の前提が変わるだろう。
アメリカの建築家、フランク・ロイド・ライト※1は、ブロード・エーカー・シティという都市計画を発表している。普通の都市は機能が集中し、高層ビルが林立するが、自動車の社会を前提にすれば、広域に機能を分散させた低密度の都市になり、自然の風景に融合するという。実現したプロジェクトではないが、アメリカらしい自動車のユートピアである。一方で、ル・コルビュジエは中層の集合住宅が密集するパリの街を否定し、都心に超高層ビルを建てることで、足下に緑の空間を確保できる「輝く都市」を提唱した。なるほど、ヨーロッパの建築家からは、ライトのような発想は出てこない。また遅れてクルマ社会に向かっていった日本では、1960年代に黒川紀章※2が、人々の移動が激しくなる時代が訪れ、カプセルが合体したり、離れたりするように、将来の建築は取り外しが可能になると予言した。これはアメリカに出現したハウストレーラーなどの自動車で移動できる住宅から着想をえている。
これらは極端な提案だが、一般的に自動車は下記のように風景を変えた。まず郊外住宅地の増殖に拍車をかけ、人々が都市の外に消費と娯楽を求めると、商業施設が集中する街のメインストリートや駅前の商店街の重要性が落ちる。一方、ロードサイドでは巨大なショッピングモールのほか、ガソリンスタンド、ダイナー、ドライブ・イン・レストラン、ファーストフードなどの店舗が発生した。そして当初は簡素な外観でしかないが、やがて速いスピードで移動する 自動車からの注意を引くために、コーヒーカップのかたちをした喫茶店など、過剰なデザインに走る。日本でも、国道沿いで順列組み合わせのように、チェーン店の看板が並ぶ「ファスト風土」的なシーンは、どこでも体験できるようになった。
路上の商業建築は俗悪なものとみなされていたが、ポストモダンの建築家ロバート・ヴェンチューリ※3は、1960年代にラスベガスのロードサイドを調査した。その成果は『ラスベガスから学ぶこと』(1972年)で発表され、カジノの街から新しいデザインの方法を導く。自動車の時代に古い美学は通用しない。彼は「装飾された小屋」の概念を発見した。すなわち、道路沿いに大きな看板を掲げ、その背後に離れて本体の建物を配置すること。近代建築は機能性のみを重視し、ユーザーとのコミュニケーションがヘタだった。しかし「装飾された小屋」は、独立した看板がクルマに対するサインの役割をはたす。建物はサインに影響されず、機能性を追求できる。ポストモダンのデザインはアメリカの路上から生まれた。
また都心において、さらに急いで交通量を増やそうとすれば、前回の東京オリンピックにあわせて出現した首都高のように、既存の道路や川の上に高架の道路を建設しなければならない。道路を立体・積層化することで、さらに高密度の利用をはかるものだが、丹下健三研究室による海上に伸びていく東京計画1960の交通計画も、3種類の速度を設定しながら、サイクル・ トランスポーテーションのシステムを提示し、こうしたアイデアを先鋭化させている。都心において自動車が増えれば、当然、今度は駐車場が問題になるだろう。限られた場所で対処するには、駐車場の高層化によって面積を稼ぐ、もしくは日本の都市のようなモザイク状の空き地が多い場合、ポケットパーキングやそのネットワーク化が有用となる。
映画に登場した自動運転のシーンで印象深かったのは、トム・クルーズ主演の『マイノリティ・リポート』(2002年)だった。2054年の未来都市において、高架道路が水平・垂直(!)にもはりめぐらされ、ポッド状の乗り物がスムーズに移動している。が、自動運転ゆえに、乗っている人が犯罪者だと判断されると、その命令に従わず、強制的に犯罪予備局に連れていかれる可能性も提示していた。なお、乗り物はそのまま高層マンションの部屋まで到着し、建物と合体する(ゆえに、おそらくカーシェアリングではない)。自動車と住宅がドッキングするイメージは、未来的なドローイングで有名な建築家集団のアーキグラム※4が提案したドライブ・イン・ ハウジング(1966年)をほうふつさせるものだった。もっとも、全体としては懐かしい未来都市のイメージにとどまっている。
やはり、移動のスピードが極端に速くなるなど、乗り物自体のあり方が根本から変わらない と、自動運転だとしても、クルマはクルマであり、建築のデザインや都市の構造のレベルにそれほど大きな影響を与えないかもしれない。仮に自動運転にとって最適化できる道路のパターンが存在するとしても、既存の街並みをそれにあわせて改造するには途方もない時間とお金がかかるだろう(道路の拡幅工事でも相当大変だというのに)。またそのパターンは、中世の都市のような、より複雑なものが適しているとは思えない。もちろん、マスダールのように、まっさらな大地にニュータウンを建設するケースもある。が、そうした場合は、自動運転が登場する以 前から、基本的にグリッドなどの整然とした街路パターンを選択していた。したがって、自動運転の導入は決定的な違いを生まないだろう。
ただし、自動運転によってカーシェアリングが進むならば、駐車場が減り、建築や都市構造にも変化を与えるかもしれない。ただし、これはハードの問題というよりも、社会がそれを推進するよう誘導する道を選択するかという別のレベルの前提に関わるはずだ。つまり、その場合、自動車の販売数が減ってもよいことを共有する。駐車場の面積を削ることができれば、都市部では公共空間が広がるだろう。もっとも、日本人は広場をうまく使いこなせない習性があって、すぐに禁止事項を羅列した看板が出てしまうのだが。また建物を使わなくなったら、とりあえず壊して、駐車場にしとけ、といった手法がなくなれば、むやみなスクラップ・アンド・ ビルドに歯止めがかかるかもしれない。
※1 1867(または1869)年生まれ、1959年没。アメリカの建築家。建築材料と環境を重視した建築を考案。日本文化に深い関心を寄せ、帝国ホテル(東京)や 自由学園を手がけた
※2 1934年生まれ、2007年没。丹下健三の門下生で建築理論メタボリズムの提唱者の一人。中銀カプセルタワービル、国立民族学博物館、豊田スタジアムなどを手がけた。
※3 1925年生まれ、2008年没。アメリカの建築 家、建築理論家。プリンスト ン大学ウー・ホール、オート・ ガロンヌ県庁舎、メルパルク 日光霧降などを手がけた。伊藤公文訳『建築の多様性と対 立性』(鹿島出版会)、安山宣 之訳『建築のイコノグラ フィーとエレクトロニクス』(鹿島出版会)などの執筆でポストモダン建築への道を開いた。
※4 1961年に創立した イギリスの建築家集団。雑誌 『アーキグラム』を発行し、未来的な都市計画を発表した。
五十嵐太郎(いがらし・たろう)
東北大学大学院工学研究科教授、建築評論家
(『モビリティと人の未来』第10章「建築/都市は自動運転をどう受け止めるか」P148-252より抜粋)
自動運転が私たちの生活に与える影響は、自動車そのものの登場をはるかに超える規模になる。いったい何が起こるのか、各界の専門家が領域を超えて予測する。
著者:「モビリティと人の未来」編集部(編集)
出版社:平凡社
刊行日:2019年2月12日
頁数:237頁
定価:本体価格2800円+税
ISBN-10:4582532268
ISBN-13:978-4582532265

自動運転によって変わるのは自動車業界だけではない。物流や公共交通、タクシーなどの運輸業はもちろん、観光業やライフスタイルが変わり、地方創生や都市計画にも影響する。高齢者が自由に移動できるようになり、福祉や医療も変わるだろう。ウェブサイト『自動運転の論点』は、変化する業界で新しいビジネスモデルを模索する、エグゼクティブや行政官のための専門誌として機能してきた。同編集部は2019年2月に『モビリティと人の未来──自動運転は人を幸せにするか』を刊行。そのうちの一部を本特集で紹介する。