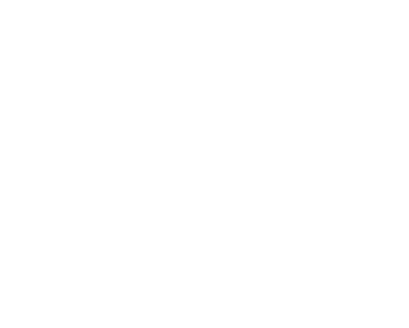青森県八戸市に昨年12月にオープンした八戸ブックセンターを今年の初夏に訪れた。噂の「市営の書店」がどのような感じなのか、事前にいろいろと想像したが、いわゆる「本のセレクトショップ」というよりも、「品揃えのいい公共図書館の分館」という感じだった。
▼館内に入ってすぐにある「フェア棚」。

人口約23万人の八戸市のような中堅都市で、大都市型の「本のセレクトショップ」を民営で成り立たせるのは難しい(東京でだって簡単なことではない)。しかし公営でやるとしても、商売として成功しすぎれば民業圧迫とみなされかねない。公共の図書施設として、公共図書館との住み分け(役割分担)も明確にしなければならないだろう。市長の強いイニシアチブのもとで実現した後も、いやむしろだからこそ、これからの運営が前例のない「冒険」であることに変わりはない。
八戸ブックセンター書棚はいわゆる「文脈棚」だ。「知へのいざない」「人生について」などのテーマに沿って、相互に関連性をもつ本が、単行本も新書も文庫も関係なく並べられている。蔵書(店頭在庫)数は現状で約8000冊。ギャラリーやその他のコーナーを含めても全体で百坪に満たないが、それぞれに工夫がこらされており、コンパクトながら密度の濃い空間になっている(フロアガイドはこちら)。
書棚は間隔を置いてゆったりと配置されていて、そこかしこにドリンクホルダーが据え付けられている。立ち読みの際はここに、カウンターで買った飲み物を置けるのだ。この仕組みは初めてみたが、ナイスアイデアである。腰を掛けられる場所もたくさんある。公共施設でありながらスタイリッシュであり、かつ細やかな気遣いもある。
▼店内で買った飲み物は、立ち読みのときはドリンクホルダーに置ける。

八戸ブックセンターは、さしあたり「書店と図書館の中間的な施設」といってよいと思う。さっさと本を選んで買って帰ってもらうのではなく、むしろ館内で本をゆっくり読めるような環境を整えている。読みたいだけここで読み、もしも気に入って本を持ち帰りたくなったなら、買い上げてくれればいい。そんな距離感を演出しているように思えた。
▼ハンモックは親子連れに人気

ハンモックに揺られて本が読めるコーナーがふたつあり、実際にお子さんと一緒にハンモックに揺られて絵本を読み聞かせているお母さんがいた。「本の塔」と名付けられた、書棚に取り囲まれて「閉じこもれる」スペースもある。ふらっと入ってきた若いカップルが、やや戸惑いつつ「ここは図書館なのかなぁ」と会話しているのも耳にした。つまり八戸ブックセンターは「書店」であると同時に、本を体験する滞在型施設でもあるのだ。
▼中に閉じこもれる「本の塔」

私が八戸ブックセンターを訪問したかった理由の一つに、この施設では「市民作家」の登録をしていることがある。八戸ブックセンターは、本を「読む人」を増やす、本を「書く人」を増やす、本で「まち」を盛り上げる、という三つの方針を掲げており、館内には「書く人」のための「カンヅメブース」がある。
▼本を書く人のための「カンヅメブース」

このコーナーには二人分の作業スペースがあり、その場所を利用するには「市民作家」に登録する必要がある。申請の際、カルテに「この賞に応募する」「電子出版で出す」など、自分で決めた方針を書き込めばよい。これから書くものの出口を具体的に示すことで書き手のモチベーションを高める、いいやり方だと思う。
「市民作家」の執筆・出版活動を支援するため、八戸ブックセンターでは今年の5月に、NPO法人日本独立作家同盟の鷹野凌さんを講師に招き、「執筆・出版ワークショップ」を行った。 「読む」ことは「書く」ことに繋がり、「読む」ことは「編む」ことにも繋がる。八戸ブックセンターが「ブックセンター」と名乗るいちばんの理由は、そのような循環をこの町に生み出すための中心となる場所だからだろう。書店でも図書館でもない、あるいは「その両方でもある」ような、「読み」「書き」の循環を生み出す場所を必要としているのは、八戸のような地方都市だけではないはずだ。
必ずしも公営である必要はない。主体は民間企業でもNPOでもいい。大学のなかにあってもいい。日本中にこのような場所がたくさんできることで、本と人の関わりは再生産され、世代を超えてつながっていくのではないか。大都市やその近郊にだって、そういう場所がもしも存在しないのであれば、作っていくことが必要ではないか。自分の住む街の近くにもこんな施設があったらという思いが、八戸を訪れてから募るばかりである。
フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。