東京大学の池上高志先生が上梓した「動きが生命をつくる」という本がある。
僕の周囲のエンジニア界隈では非常に話題になった本で、内容としては人工生命の起源から現在までを俯瞰した論文をまとめたもの。
池上先生といえば、人工生命研究の第一人者として知られている。
ところが、人工生命という言葉は、人工知能ほどには知られていない。
人工知能というのはよく漫画や映画に出てくるが、人工生命という言葉はあまりそういうものに出てこない。
ただ、実は我々はごく日常的に人工生命の研究成果を応用したものを目にしている。
たとえばゲームやテレビ、映画などで頻出する、キラキラした光の粒が意味ありげに動くような動き。
ハリウッド大作に登場する無数の動物や人々、鳥といったもの、そうしたものは人工生命の研究の影響を多分に受けている。
最近では、ウィルスの伝搬を数値シミュレーションするのが一般的になったが、これもまた人工生命研究の過程で生まれたものである。
そもそも、人工生命の起源は、コンピュータ発明とほぼ同時に現れる。
世界最初のコンピュータの一つ(※諸説あり)として知られる、ペンシルバニア大学のENIACの開発に立ち合い、それを理論化したフォン・ノイマンは、晩年の研究テーマとして、「自己増殖する機械」を数学的に証明することに情熱を捧げた。
自己増殖、つまり機械がまるで生物のように、自分の子供を産み育てるという現象である。
これが果たして可能であるかどうか、それを数学的に証明しようとしたのがノイマンだった。
ノイマンは自己増殖する機械の実現が可能であることを証明するために、非常に簡易な数理モデルを作った。
機械によって作られた細胞が隙間なく敷き詰められた環境で、それぞれの細胞が周囲の細胞とだけ情報交換をしながら相互作用する環境である。
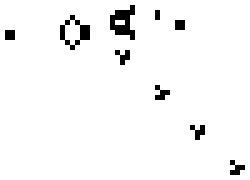
出典:https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_automaton#/media/File:Gospers_glider_gun.gif
これをセル・オートマトン(細胞自動機械)と呼び、その後、セル・オートマトンの研究は引き継がれ、さまざまな災害のシミュレーションや自然環境のシミュレーション、環境汚染のシミュレーションなどに応用され、セル・オートマトンをより柔軟に拡張したマルチエージェントシステムは、ほとんどのゲームの起源となった。
実は筆者が10代の頃にゲーム業界を志したのも、人工知能と人工生命を仕事で扱うには、ゲーム業界くらいしか食い扶持がなかったからだ。
人工知能の起源もノイマンと時代を同じくするアラン・チューリングだったと考えると、人工生命と人工知能は双子の兄弟のようでありながら、互いに全く別の進化を遂げていった。
人工生命と人工知能が似ているところは、互いに、「理由はわからないが、とりあえず生命の形式を数値シミュレーションで模倣しよう」というアイデアから始まっていることである。
人工生命であるセル・オートマトンは非常に簡単なルールで記述できる。ルールが簡単だからそれが生命のように見えることは奇妙ですらある。
人工知能であるニューラルネットワークも、非常に単純なルールで記述できる。ルールが簡単だからそれが知能のように振る舞うことが長らく信じられてこなかった。今でもそうかもしれない。
しかし、人工生命の動きは生物の動きによく似ている。
たとえば、鳥の動きを単純なルールで真似るboidsという人工生命は、非常に複雑で生命的な動きを見せるが、ルールは非常に簡単である。そして映画やゲームなどで飛び交う鳥や動物の群れの動きというのは、boidsを起源としている。
たとえば避難経路のシミュレーションなどはboidsと同じマルチエージェントシステムを使って人々の動きを予測する。
マルチエージェントシステムとは、人工生命一体を「エージェント」と定義し、複数のエージェントが相互作用することによって成り立つシステムである。
boidsでは鳥がエージェントであり、避難経路シミュレーションでは人がエージェントとなる。
エージェントの振る舞いは難しくても単純でもいい。
避難シミュレーションや鳥の群れのシミュレーションの場合、かなり単純なエージェントでいい。
人が避難しようとするとき、社会的地位やその人の性格といったものはほとんど避難行動に影響せず、身体能力や体重や身長といった要素の方が遥かに重要だ。
筆者自身は2003年に上梓した「ゲームデザイン誇大妄想狂(絶版)」の中で、マルチエージェントによる恋愛シミュレータというものを紹介している。
人の特徴や心の動きを数理モデル化してエージェントとし、誰がどの人とどれくらい仲が良いか、一緒に会話したりご飯を食べたりしてくっついたり離れたり、さながらトレンディドラマのような物語を繰り出すというシミュレータだ。
それがなんの役に立つのか、という疑問が浮かぶかもしれないが、ただ面白いからやっていただけだし、「ただ面白いから」が許されるのがゲーム業界である。
実際、似たようなアイデアがゲーム化されたのが2009年に任天堂から発売された「トモダチコレクション」である。
実は人工生命とゲームの関わりは深く、たとえば都市運営ゲームのシムシティや、人間関係ゲームのシムズは、そのまんま人工生命をゲーム化したものである。
シムシティでは公害や犯罪、地下といったものがセル・オートマトンでシミュレートされているし、シムズはそのまんまマルチエージェントシステムを楽しむゲームである。
これまで人工知能と人工生命は全く無関係なものと考えられてきた。
というのも、出発点は互いに「生命活動を模倣して数理モデル化する」ところから始まったものの、注目する点が人工知能では知能、人工生命では生命活動そのものに分離していたためで、人工生命の方が目的が単純なためゲームやシミュレーションなどで実用化されるスピードが早かった。人工知能は、長年、知能が自発的に学習するという現象を再現しきれずに苦しんだ。
2012年以降でディープラーニングが広まり始めると、人工知能が人間よりも高い学習能力を持つのは当たり前と考えられるようになった。
こうして、ある意味で人工知能が人工生命の進歩に追いついたことで、人工知能と人工生命は今、急速に接近しつつある。
自己対戦を繰り返すアルファ碁や、ライバルAIと競って学習するグランツーリスモソフィのような強化学習も、一種のマルチエージェント環境であり、これまでほとんど交流のなかった人工生命分野と人工知能分野は近年急速に接近しつつある。
たとえば、生命現象の一つ、遺伝をシミュレートした遺伝的アルゴリズムは人工生命由来の技術だが、人工知能の設計に遺伝的アルゴリズムが積極的に用いられるようになってきた。
Google Cloud AutoMLや、IBM AutoAIといったクラウド型のニューラルネットワーク設計システムは遺伝的アルゴリズムを始めとする自動設計アルゴリズムを使っている。
筆者の所属するギリア株式会社でも、Ghelia Spectreという独自の遺伝的アルゴリズムを利用したニューラルネットの自動設計ソリューションを提供しており、すでに大手半導体メーカーで積極的に採用されている。
遺伝的アルゴリズムによって設計されたニューラルネットは、人間が設計したものよりも1/100ほどのコンパクトなサイズに収まり、これによって必要なメモリや計算量も1/100になる。これまで小さい部品には載せられないと考えられていた人工知能が乗るようになり、これは半導体の性能が100倍になるのと同じ効果がある。
遺伝的アルゴリズムによる人工知能の設計というアイデアを最初に聞いた時は、非常に大胆で野心的と感じたが、同時に妙にしっくり来たような感覚に陥った。
人工知能の根幹を成すニューラルネットワークは、そもそも生物の神経細胞網を数理モデル化したものだから、この設計を最適化するのに、人工生命技術である遺伝的アルゴリズムを使うのはむしろ当然のようにも思える。
人工知能研究者の多くは、人工知能研究の先には、知能の再現という結果があると信じている。
むしろ知能を再現するためにその周辺を研究していたのだが、最も難しかったのが、脳の再現だ。
脳を再現したら、次は身体であり、身体の次は、複数の身体である。
脳と身体と、複数の身体からなる社会を再現するとすれば、それはもはや人工生命である。
一方で、人工生命の研究者たちは、人工生命の「生命性」について、人工知能研究者とは完全に異なる視点を持っているように思える。
それが端的に表現されたのが「動きが生命をつくる」という言葉なのではないだろうか。
なぜなら、人工知能の研究者は、誰もそんなふうに思っていないからだ。
「動きが生命をつくる」というのは、「生物とは、動きである」という捉え方だ。それが化学的なメカニズムで動いているか、機械的なメカニズムで動いているかは関係ないという考え方だ。
今、一般的に知られている生命現象は、化学的メカと考えられる。これは生命化学と呼ばれる研究分野で研究されていることだ。
一方、人工生命の研究では、その生命が化学的メカであるか、機械的メカであるか、数理モデルであるかを区別しない。
つまり、生命vs機械ではなく、どちらも生命として扱うのである。
微生物や細菌を用いた人工生命の研究というのもあり得る。それが数理モデルと同じ振る舞いをするとき、どちらかを偽物とは呼ばず、どちらも生命として捉える。なぜならば、「動きが生命をつくる」からだ。
この倒錯は、生命を捉えるときのコペルニクス的展開と言える。
つまり、普通は「生命が動いている」と考えられている。しかし、池上先生は「動きが生命現象の本質であり、動いていれば生命と捉えることができる」という視点を提供したのだ。
コペルニクスは、地球の周りを太陽が回っているという天動説が一般に信じられていた時代に、太陽の周りを地球を始めとする惑星が回るという視点を提供した。
この話の重要なところは、「どちらにせよ単なる捉え方の問題であり、自然現象は変わらない」ということだ。
つまり、地動説で捉えようが天動説で捉えようが、自然現象そのものは変化しない。単に人間の認識の問題である。
そして天動説で考えると面倒なことが地動説ではスッキリする。だから認識しやすい。それだけのことなのだ。
このような認識の変化は、人工知能にも必要とされているのではないか。
先日行われたソニーCSLのオープンハウスのオンライン講演の中で、錯覚する人工知能が紹介された。
人間が見て混乱する錯視と同じ現象を起こす人工知能を使うと、逆説的に人間が錯覚する錯視を人工知能が作り出すことができるというのだ。
人間が意識だと考えているものが、実は大雑把に現実世界の認識を要約したものだと考えられてきている。
人間が自分の意思で行動したと思っていることも、実は出発点は意識そのものではなく、行動してから意識が形成されるとする実験結果がいくつも見つかっているのだ。
手品師はそうした意識の錯誤を利用してマジックを成立させ、我々は日常生活でもさまざまな錯覚を利用して生きている。
これは根本的に、人間は目や耳や皮膚から入ってくる膨大な情報を全て同時に認識することはできないことに原因があり、錯覚というのは情報を要約するときに生まれるノイズである。
しかし、この錯覚をうまく利用すると、ユヴァル・ノア・ハラリが指摘するように、共同体や経済や友情や連携といった幻想を共有することができる。
ただし、そもそも「正しい要約」というものはなく、それが一人一人の「感じ方の違い」になっていく。これが個性と呼ばれる。
そして人工知能も、初期状態からランダムに学習していくため、全ての人工知能はコピーしない限りはふたつとして同じものにはならず、個性がある。
そして人工知能も錯覚することができることが示された。
人工知能が錯覚を獲得するということは、人工知能が人間との間に仲間意識を感じたり、共同体を形成したり、経済に積極的に関与していく可能性も生まれる。
もちろんそこまで言ってしまうとまだSF的な誇大妄想に過ぎないが、知能において錯覚が場合によっては知覚そのものよりも重要になってくる場面がありそうだ。

新潟県長岡市生まれ。1990年代よりプログラマーとしてゲーム業界、モバイル業界などで数社の立ち上げに関わる。現在も現役のプログラマーとして日夜AI開発に情熱を捧げている。

