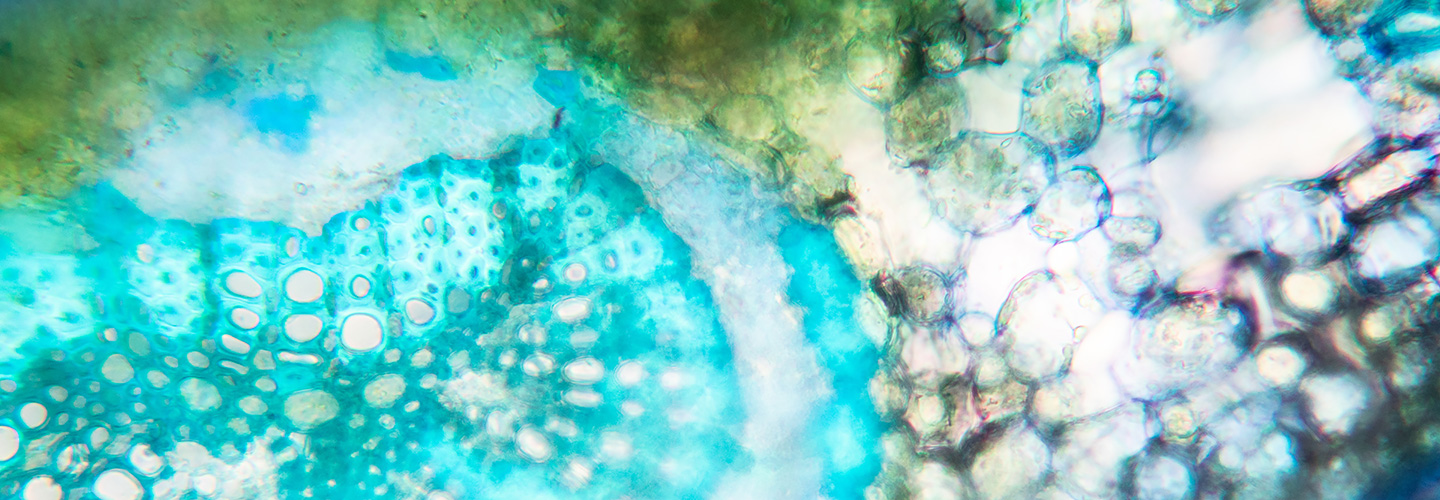
original image: sinhyu / stock.adobe.com
November 15, 2022
yomoyomo yomoyomo
雑文書き/翻訳者。1973年生まれ。著書に『情報共有の未来』(達人出版会)、訳書に『デジタル音楽の行方』(翔泳社)、『Wiki Way』(ソフトバンク クリエイティブ)、『ウェブログ・ハンドブック』(毎日コミュニケーションズ)がある。ネットを中心にコラムから翻訳まで横断的に執筆活動を続ける。
この10年ほど、だんだんに同年輩の人たちの死を意識するようになっている。私たちの世代は去ろうとしていて、誰かが亡くなるたびに、まるで剥離(はくり)のように、自分自身の一部を引き裂かれるように感じる。私たちがこの世を去れば、私たちのような人間は誰もいなくなるのだが、そもそもほかの人と同じような人間などいないのだ。人が死んだとき、誰もその人に取って代わることはできない。(オリヴァー・サックス)
世間は新しいものを価値として要求する。百番指したという大山、升田戦が棋技としていかに至宝のごとき内容を持つものであっても、その人としての限界を越えることは出来ない。そこで世間はちがった“人”を要求し、その限界を破ろうとする。これが歴史とか生命とかいうものの命令なのだろう。(金子金五郎)
2022年もそろそろ終わりが見えてきましたが、今年もいろいろな方が亡くなりました。読者の皆さんそれぞれに、惜しく思う人がいるでしょう。個人的な事情によりますが、ワタシ自身はこの10年ほど、自分の両親世代の訃報が特に気になっており、そうした意味で今回は、今年3月に85歳で亡くなった建築家、都市計画家のクリストファー・アレグザンダーをまず取り上げたいと思います。
この連載が通常扱う話題を考えれば、建築家の話は場違いに思われるでしょうか。ワタシがクリストファー・アレグザンダーの仕事をちゃんと知るのは、2009年に刊行された江渡浩一郎『パターン、Wiki、XP――時を超えた創造の原則』を読んで以降になります。
ワタシは2002年に『Wiki Way コラボレーションツールWiki』を訳し、その後、Wiki並びにその周辺の話題を語り合う「Wikiばな」というコミュニティに関わりがあったため、刊行当時はそれほど違和感はなかったのですが、改めて読み直すと『パターン、Wiki、XP』は、半分近くの分量をクリストファー・アレグザンダーの話に割く、想定読者層を考えると結構挑戦的な本だったと思い当たります。
しかし、『パターン、Wiki、XP』は、その表紙にもあるように、ソフトウエア設計の定石集「デザインパターン」、アジャイル開発手法「エクストリーム・プログラミング」、そして知のコラボレーションシステム「Wiki」の3つの起源は、クリストファー・アレグザンダーの仕事に起源があることを解き明かす本であり、その構成は必然なのです。
上の段落でカッコ書きした「デザインパターン」、「エクストリーム・プログラミング」、「Wiki」にまつわる熱狂というか評価がある程度落ち着いた現在、10年以上ぶりに『パターン、Wiki、XP』を読み直すと、クリストファー・アレグザンダーという人の仕事に自然とフォーカスがいきますし、改めてそれにシンパシーが湧くように思います。
アレグザンダーは建築の外面的な美ではなく、「何がものを美しくするのか」の原理を一貫して追い求めた人ですが、面白いのは『形の合成に関するノート』(1964年)で設計(デザイン)のプロセスを数学的な手続きに定式化して大きな反響を呼んだのに、サンフランシスコのベイエリア高速道路の計画立案に携わった後、『都市はツリーではない』(1965年)において「ツリー」と「セミラティス」を対比させることで、人工都市のツリー構造を批判する側に回ったことです。
これは『形の合成に関するノート』で論じた数学的な形式化に対する自己批判とも言えます。これからアレグザンダーは、トップダウンで計画される人工都市のツリー構造ではなく、ボトムアップな生成的で斬新的成長によりできあがる自然都市が持つセミラティス構造をどうやって実現するかを探求するわけですが、この転回は近代都市計画を激烈に批判し、都市における多様性と混在の重要性を説くジェイン・ジェイコブズ『アメリカ大都市の死と生』(1961年)に共鳴するものでしょう。
ワタシなど「都市はツリーではない」というカウンターカルチャーな言い切りがグッときたわけですが、トップダウンの数学的な設計ではなく、建築の利用者も設計に参加するための建築家と利用者にとっての共通言語としての「パターンランゲージ」も、自然都市や生き生きとした建築や街が備える特性を指す「無名の質」にしても、なんとなく分かる、分かるぞ! と『パターン、Wiki、XP』を読んで盛り上がったものです。が、実際にアレグザンダーの著作に手を出し、その盛り上がりのままご本尊の思想を理解できたとは残念ながら言えません。
それは、ワタシ自身が建築にしろ都市計画にしろ門外漢だからというのもありますが、特に「無名の質」などかっちり説明しようとするとその本質が逃げていくような、ともすれば神秘主義と見られてしまう説明の難しさによるところが大きいです。New York Timesの追悼記事にも引用されている「私は人の顔に浮かぶ微笑みのような建築を作りたいんだ」というアレグザンダーの言葉も分かる気がするし共感もしますが、でも、何をもってそう言えるのか、ワタシには説明できません。現実にアレグザンダーの方法論は必ずしも成功しませんでした。
磯崎新による紹介によりその方法論が早くに認知された日本でも、アレグザンダーが手がけた1980年代の盈進学園東野高校が、利用者参加の直営方式の施工を徹底できず、日本の伝統的な建築とゼネコンによる施工が混在することで賛否両論の出来となりました。また90年代に、モダニズム建築の批判者として知られるイギリスのチャールズ皇太子(現チャールズ3世)のアドバイザを引き受けたのが欧米の建築業界との関係を悪化させ、建築ジャーナリズムに取り上げられることも少なくなくなります。
しかし、彼の「パターンランゲージ」などの方法論は、ウォード・カニンガムとケント・ベックによりソフトウエア開発の世界に取り入れられ、大きな成果を生むこととなります。ケント・ベックは、建築の利用者と設計者とが一致する世界を求めながら、建築の詳細を最終的に決定するのは建築家であるという姿勢を崩さず、また一方で利用者は自分たちの建築に対する要求を伝える術を持たなかったことをアレグザンダーの失敗の原因と分析し、一方でソフトウエア開発における開発者と利用者はまだ固定的な関係に至っておらず、ソフトウエアで(エクストリーム・プログラミングにより)新たな社会構造を作る機会があると宣言しました。
ケント・ベックは、アレグザンダーの利用者と設計者とが一致する世界という目標設定は否定しておらず、むしろそれをソフトウエア開発の世界で実現しようとしたわけですが、どうしても成果が固定的でやり直しが難しい建築よりも、それが容易なソフトウエア開発のほうがアレグザンダーの目標設定に向いていたのも大きいと思います。アレグザンダーに多大な影響を受けたスチュワート・ブランドの『How Buildings Learn: What Happens After They’re Built』(1994年)のような建築が完成した「後」に着目するユニークな仕事もありますが、建築とソフトウエア開発には共通点も確かにあるものの、成果の可塑性のレベルがまったく異なります。
さて、都市計画家としてのアレグザンダーは、トップダウンで計画される人工都市のツリー構造に反発しました。21世紀の現在、昔ながらの人工都市、ニュータウン開発の話はあまり聞かなくなりましたが(もっとも西沢大良氏によると、中国で量産された近代都市は、典型的な60年代風の計画都市らしい)、今では「スマートシティ」という言葉が完全にそれにとってかわった印象があります。岸田文雄首相が就任早々ぶちあげたものの、じきに何も聞かなくなったデジタル田園都市国家構想とやらもその系譜でしょうか。
ジェイコブズやアレグザンダーが批判した都市計画の時代とは違いますが、センサーで収集した大規模データを基にしたAI(アルゴリズム)によるソリューションがご神託扱いされ、都市自体がそうしたご神託に合わせて最適化されることで、かつてとは異なる「都市のツリー構造」による「人間の疎外」が起こるのをワタシは危惧します。
「スマートシティ」の批判的考察とそれを良いものにしようとする仕事として、この連載でも過去「反応が良い都市と市民のテクノロジー」でスーザン・クロフォードらの『The Responsive City』を取り上げましたし、AIを駆使したスマートシティ計画におけるテクノロジー解決主義の危険性を北米の豊富な事例を踏まえて論じるベン・グリーン『スマート・イナフ・シティ──テクノロジーは都市の未来を取り戻すために』のような優れた書籍がありますが(謝辞で真っ先にスーザン・クロフォードの名前が挙げられています)、ここではニュースクール大学の人類学の教授であるシャノン・マターンの『A City Is Not a Computer: Other Urban Intelligences』を取り上げます。
ここまで読まれた方なら、この書名がそのままアレグザンダーの『都市はツリーではない』の現在的な言い換えなのだとピンとくるでしょう。しかし実は、シャノン・マターンが2017年に「都市はコンピュータではない」を書いたとき、頭にアレグザンダーのことはなかったようです。彼女のインタビューによると、「都市は情報処理機械である」というテーマの本に寄稿を求められ、確かにそういう部分はあるが、都市を情報処理機械に置き換えてしまうと、都市に内在するその他のもっと重要な認識論的機能、知識、知恵を除外してしまうことになると反発し、挑戦的にも「都市はコンピュータではない」と言い切る文章を書いたのだそうです。
その後でマターンは、アレグザンダーの『都市はツリーではない』のことを教えられたそうで、改めてアレグザンダーの著作を研究し、古いものの上に新しいものを構築する「接ぎ木(graft)」というコンセプトを提示しています。
また『A City Is Not a Computer』は、「スマートシティ」と新型コロナウイルスによるパンデミックとの関係をとらえている点もポイントでしょうか。マターンは別のインタビューで、新型コロナウイルスが主題の本にはしたくなかったが、自分が抱いていた多くの疑問に哲学的、歴史的な文脈を与えてくれたと語っています。
マターンは「都市のダッシュボード」という言葉を使っていますが、例えば都市のヒートマップや新型コロナウイルスの新規感染者の推移などの都市のデータの中央集権化の象徴ともいえるダッシュボード、コンソールルームからこぼれ落ちるもの、ダッシュボード化できない都市に存在するインテリジェンスについてのオルタナティブを考察し、その一例としてマターンは図書館を挙げます。もちろん図書館も、流通管理システムを使ってサービスを運営しており、政治家は図書館の経済的な意義を言いたがりますが、図書館などの文化施設がコミュニティに提供する価値には、測定不可能であったり、少なくとも短期的でないものがあるのをマターンは強調します。公園もそうですが、社会的なインフラであり、公衆衛生的な価値もあるが、教育的な空間でもあるというように(このあたりにアレグザンダーの言うところの「セミラティス」を連想し、継承を感じます)。
都市システムをデータとして測定可能なものにし、都市システムのすべてのリアルタイム監視を約束するからこそ、ハイテク企業が都市行政に製品を売り込むのに成功しているとマターンは指摘したうえで、そうしたソフトウエアの指示に従うのは政治的な選択だが、政治家は倫理的に問題があったり、政治的に複雑な問題をソフトウエアにアウトソースできるのに安心感を覚えていると苦言を呈しています。このあたりは『スマート・イナフ・シティ』にも重なる問題意識です。
また『A City Is Not a Computer』を読むと、膨大な計算やデータを駆使することで全知全能という誤った感覚をもたらす「都市のダッシュボード化」が近年になってはじめて出てきた話ではなく、中央集権的な都市データのパノプティコンへの欲望は、それこそコンピュータの歴史程度には長く存在しているということです。人間を疎外する「スマートシティ」に一市民が抗うことは難しいですが、都市住民の政治参加の意思が重要なのは言うまでもありません。それを考える上で、利用者と設計者とが一致する世界を目指したクリストファー・アレグザンダーの苦闘は、今なお示唆を与えているように思うのです。